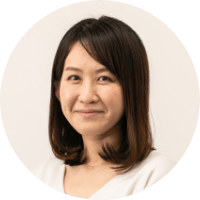本社の保険金サービス企画部で災害対策本部のコントローラー役を幾度となく担っている小川さん。同様にコントローラー役の経験をもち、現地の災害対策本部にも頻繁に駆けつけている早川さん。そして、九州保険金サービス第二部の江崎さんは、近年の大規模災害の多くの事案で災害対策本部に入り、熊本地震では自身が被災を経験している。そんな3人が尽力する災害対策本部とは、どのようなものなのだろうか。
「基本的に災害発生地区を管轄する担当役員が災害対策本部長になり、現地の保険金サービス部長が副本部長に就きます。その下に所属する保険金サービス課長と保険金サービス企画部などのメンバーで構成されたコントローラー席が入り、全体を統括します。そして、電話受付、書類管理、現場調査、保険金支払いなど具体的な役割をもつ班が8つほど編成されます」と語る小川さん。


保険金サービス企画部 2005年入社 小川さん
「台風ですと、被害件数1万件で、ピーク時で概ね90人の要員が必要になります。2018年9月の台風21号・24号では、過去最高となる延べ5000人が集結しました。このときの対策本部の規模は、過去にない規模感でしたが、近年では延べ数百人体制になることが多いですね。通常は現地の保険金サービス部で対応して、人数が足りなかったら現地の営業部門の社員や本社内勤部門の社員、それでも足りない場合は全国に応援を依頼します」と語る小川さん。さまざまな部門からこれだけの人数が集結する対策本部は、さぞ混乱するのではないだろうか。
「だいたい2週間単位で応援部隊が入れ替わっていきます。災害規模に応じた必要人数を割り出して調整したり、対策本部で働いている社員の声を吸い上げたりするのもコントローラー席の役割です。私は2018年9月の台風21号・24号の際にコントローラー席でした。みんなに顔を覚えてもらい、何かあったら相談してもらえるよう、毎朝必ず全員にあいさつしてまわりました」と、早川さんが当時の工夫を語る。


保険金サービス企画部 2010年入社 早川さん
一方、大人数を応援に送り出した部署は、人手が足りない状況に追い込まれる。
「課によっては、複数の人を同時に応援に送り出すケースもあり、応援社員の業務フォローに追われることもあります。でも、お客さまにいち早く保険金をお届けしたいのは、全社員共通の思い。応援社員を応援する気持ちで、残ったメンバーも業務に注力しています」と語る江崎さん。「ほんと、そうです。災害応援で人が少ないから大変という社員はだれ一人いません。残ったメンバーの協力も含めて災害対応なのです」と、早川さんも全社一丸を強調する。


九州保険金サービス第二部 2007年入社 江崎さん